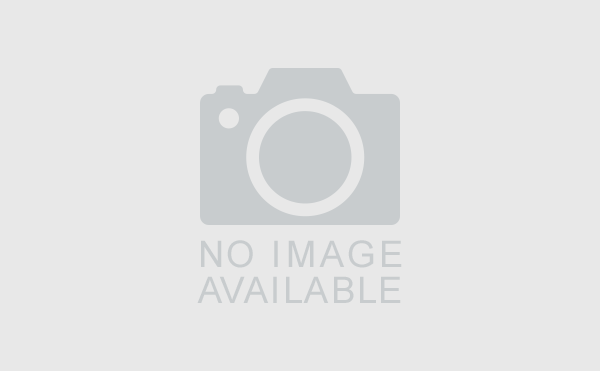雑学(2)学(まなぶ)の語源
あとがきの所で、正=「ただしい」の語源について述べましたが、
漢字には、色々な意味を持って集まって成り立っています。
漢字の一、二、三も順に棒の本数が増えて、漢字ができています。
土=(つち)は、ーという平らな大地に+という木が生える大地を
表しています。

大の横棒は、大地を表しています。
木は大地にしっかり根を張って立っている状態を表しています。

ここから大きな人や大木には、大地の中に目に見えない根があるから
簡単には倒れない。
小という字には、― という大地部分がないから風が吹くと
あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまう様を表現しています。
又、木がたった一本では、ただの木ですが、二本になると林になり
三本になると森になります。
学の上の部分は、山冠と家冠の合成形になります。
又、下の子は、鳥の子供を現わしています。

これは、森の中の鳥の巣を表しています。
つまり、子鳥が巣の中から、親鳥が飛んでいるのを見て
自分も羽ばたく練習をしている様を学(まなぶ)と言っているのです。
子鳥が、早く巣立って、親のように飛びたいということです。
これをもう少し分解すると
まな=眼=見る事、「眼差し」ともいう事があります。
又、「まな娘」と言って、目に入れても痛くないくらい
かわいがる譬えの意味を表す言葉があります。
ぶ=振り=羽を羽ばたかせる
これから「学」を「まなぶ」として読むようになった。
他には「まねぶ」からの転とも言われています。
どちらにしても、漢字にはこのような語源=意味があるという事です。
私たちは、何事も、親鳥に例えるようなものを手本にして学び、
又、反対にそうならないように学ぶこともあります。
最近は、何が正しいか、正しくないかが、分かりにくくなっています。
誰が正しいかでなく、何が本当に正しいかを見極める術を身に着ける事
それを貫くことが大事だと思います。
私たち、生きている限り、常に学ぶことばかりです。